阿波の国:発心の道場
|
1番〜23番札所 伊予の国:菩提の道場
|
| 1番札所 竺和山 霊山寺 拡大 |
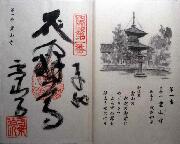 |
 |
 |
大きな仁王門に 「竺和山」 の金文字、そして 「四国第一番霊山寺」 の石標、多くのお遍路
さんがここから打ち始めているようです。 「南無大師遍照金剛」 と書かれた白衣に袖を通すと、気恥ずかしいような、気の引き締まる
ような思いになります。 鈴をぶら下げた頭陀袋に、納経帳・納め札などを入れ、「心で祈ればいいんですよ」 の一言
に押されにわか信者の巡拝が始まった。 所在地 徳島県鳴門市大麻町板東
|
| 2番札所 日照山 極楽寺 拡大 |
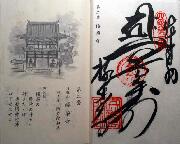 |
 |
 |
1番札所から 1.4km。
参道の極楽橋を渡って朱色の鮮やかな仁王門をくぐると、綺麗な庭園が拡がり境内奥の傾
斜のきつい石段を登ると本堂です、 大師手植えの長命を願う 「長命杉」、そして、お釈迦様の足跡といわれる 「仏足石」 があり
ます。 所在地 徳島県鳴門市大麻町檜
|
| 3番札所 亀光山 金泉寺 拡大 |
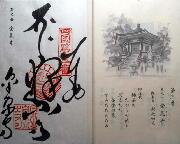 |
 |
 |
2番札所から 2.6km。
朱塗りの仁王門をくぐると正面に本堂、その手前右に大師堂と八角形の観音堂が、左側に
は鐘楼が姿を見せます。 弘法大師が掘ったと伝える 「黄金の井戸」 があり、この水を飲むと長寿になるとか。
また、この地に立ち寄った弁慶が力だめしに持ち上げたと伝える 「弁慶の力石」 もあります。
所在地 徳島県板野郡板野町大寺
|
| 4番札所 黒巌山 大日寺 拡大 |
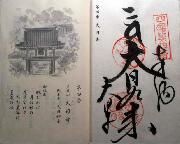 |
 |
 |
3番札所から 5.0km。
人里離れ、山に囲まれた落ち着いた雰囲気の札所です。
木々の緑に映える朱色の鐘楼門が美しい。
所在地 徳島県板野郡板野町黒谷
|
| 5番札所 無尽山 地蔵寺 拡大 |
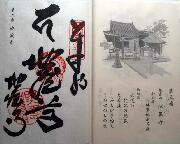 |
 |
 |
4番札所から 2.0km。
仁王門の先右に大銀杏がそびえ、その奥が太子堂、左奥が本堂です。
本堂裏手の石段を上がると、奥の院の羅漢堂があります。
|
| 6番札所 温泉山 安楽寺 拡大 |
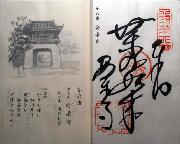 |
 |
 |
5番札所から 5.3km。
中国風?な鐘楼門の先、正面の本堂は銅葺きの綺麗な鉄筋コンクリート造りです。
極彩色の多宝塔が 「逆松」 という老木の緑に冴え、その前の池にはたくさんの鯉が泳いでい
た。 山号が示すとおり、かっては諸病に効くという温泉が湧き、お遍路さんの疲れを癒していた
とか。 所在地 徳島県板野郡上板町引野
|
| 7番札所 光明山 十楽寺 拡大 |
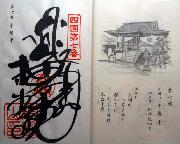 |
 |
 |
6番札所から 1.2km。
6番札所と同じ朱色と白の中国風?な鐘楼門が印象的です。
寺号は、人間が受ける生や死、病、老いなど八つの苦難を離れ、極楽浄土に往生する者が受
ける十の光明に輝く楽しみが得られるようにと、願いが込められているとか。 所在地 徳島県板野郡土成町高尾
|
| 8番札所 普明山 熊谷寺 拡大 |
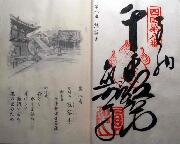 |
 |
 |
7番札所から 4.2km。
駐車場から参道を登って行くと、四国霊場では最大規模の堂々たる仁王門があります。
その門をくぐり、さらに坂や石段を登ると右に弁天池、左に美しい姿の多宝塔が、さらに進むと
本堂、本堂左の石段の上が大師堂です。 境内は大きな音で御詠歌が流れていました。
所在地 徳島県板野郡土成町西原
|
| 9番札所 正覚山 法輪寺 拡大 |
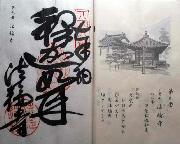 |
 |
 |
8番札所から 2.4km。
広々とした田園、のどかな風景に溶け込むような寺です。
白い土塀で囲まれた境内、大小の草鞋を納めた仁王門の先に本堂と大師堂があります。
四国札所八十八ヶ寺で、涅槃像を本尊としているのはこの寺だけでのようです。
所在地 徳島県板野郡板野町土成
|
| 10番札所 得度山 切幡寺 拡大 |
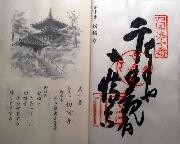 |
 |
 |
9番札所から 3.8km。
かなり急な坂道を登った山の中腹、標高150mにあります。
朱塗りの山門をくぐり 「男やくよけ坂」 「女やくよけ坂」 などと刻まれた急な石段を 330段登る
と正面に本堂、その右に大師堂があります。 本堂下の狭いスペースに数台駐車していた、石段左の参道を車で登っても良いのかも。
所在地 徳島県阿波郡市場町切幡
|
| 11番札所 金剛山 藤井寺 拡大 |
 |
 |
 |
10番札所から 9.3km、車 13km。
仁王門をくぐると、右に弘法大師が苗木を植えたと伝える大きな藤棚、左に鐘楼、奥の一段
高いところに本堂、その右が大師堂です。 本堂左側に 「へんろ道」 の標識があった、歩き遍路で名高い焼山寺への 「遍路ころがし」
と云われる難所があるらしい。 所在地 徳島県麻植郡鴨島町
|
| 12番札所 摩盧山 焼山寺 拡大 |
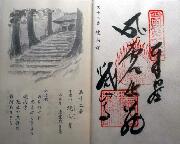 |
 |
 |
11番札所から 12.9km、車 43kkm
昔から 「一に焼山、二にお鶴、三に大龍」 と云われた難所の一つで、標高 700mに建つ寺
です。 11番から遍路道を歩けば 6時間、いま車で山門近くまで行けます。 仁王門をくぐると、見事な老杉が参道両側に並び荘厳な雰囲気を漂わせています。
幹回り 5m前後の巨木は天然記念物に指定されており、仁王門付近だけで 40本余りあるら
しい。 所在地 徳島県名西郡神山町下分
|
| 13番札所 大栗山 大日寺 拡大 |
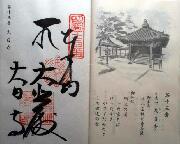 |
 |
 |
12番札所から 20.8km、車 30km。
焼山寺から里へ下りた道沿いにある、こじんまりとした落ち着いた感じの札所です。
山門をくぐると正面に 「しあわせ観音像」 があり、左が本堂、右が大師堂です。
所在地 徳島県徳島市一宮町西
|
| 14番札所 盛寿山 常楽寺 拡大 |
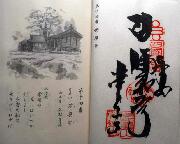 |
 |
 |
13番札所から 2.3km。
この札所には山門はないようです。 石段を登ると 「流水岩の庭園」 と呼ばれている大岩
盤でできた起伏にとむ境内が広がっています。 本堂に覆い被さるように枝を広げているイチイの大木があり、枝別れしている所に小さな大
師像が祀られ 「あららぎ大師」 と呼ばれ親しまれています。 所在地 徳島県徳島市国府町延命
|
| 15番札所 薬王山 国分寺 拡大 |
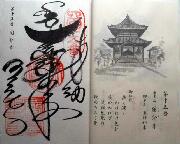 |
 |
 |
14番札所から 0.8km。
聖武天皇が天下太平を祈願して全国各地に建立したのが国分寺です。
四国には 4つの国分寺があり、ここは田園地帯に建つ寺で少し荒れた感じです。
石橋を渡り山門をくぐると、正面に本堂、その右に大師堂、左に鐘楼があります。
所在地 徳島県徳島市国分町
|
| 16番札所 光耀山 観音寺 拡大 |
 |
 |
15番札所から 1.8km。
古い町並みの中に佇む 小ぢんまりとした寺で、山門の両側には寄進者の名前と金額を書
いた石柱が塀のように建ち並んでいます。 山門をくぐると、目の前が本堂、右が太子堂です。
所在地 徳島県徳島市国分町
|
| 17番札所 瑠璃山 井戸寺 拡大 |
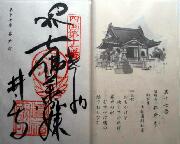 |
 |
 |
16番札所から 2.8km。
大師が掘ったと伝える 「面影の井戸」 が本堂手前左にある日限大師堂の中にあります。
覗き込んで自分の姿が映れば無病息災、映らないときは不幸が訪れるとか。
大師の井戸や霊水にまつわる話しは各地にあるが、その伝説が寺号となっています。
所在地 徳島県徳島市国府町井戸
|
| 18番札所 母養山 恩山寺 拡大 |
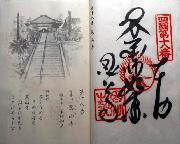 |
 |
 |
17番札所から 16.8km、車 20km。
郊外の小高い山の中腹、修行大師の立像が迎えてくれます。
左側の石段を登ると左側に大師堂、さらに正面の石段を登ると本堂です。
大師が修行中この寺は女人禁制でした。 母堂が訪ねられたとき女人開禁の秘法を修して
成就、母堂を寺内に迎え入れたと伝えます。 そして、寺号を母養山恩山寺と改めたという。 所在地 徳島県小松島市田野町
|
| 19番札所 橋池山 立江寺 拡大 |
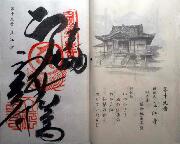 |
 |
 |
8番札所から 4.0km。
阿波の関所寺として知られてます、罪人や邪心を持つ者は大師のおとがめを受け先へ進め
なくなるとか。 関所寺は各国に1ヶ寺、四国には4ケ寺あります。 山門をくぐると、左に本堂と鐘楼、右に大師堂と多宝塔がそびえています。
所在地 徳島県小松島市立江町
|
| 20番札所 霊鷲山 鶴林寺 拡大 |
 |
 |
 |
19番札所から 13.1km。
お鶴さんと地元の人々に親しまれている寺で標高 500mにあります。
焼山寺に続く難所で多くの遍路を泣かせてきたらしいが、いま車で仁王門近くまで行けます。
巨木杉の立ち並ぶ参道の先に仁王門、正面奥の護摩堂から右に伸びる長い石段を登り切
ると本堂です。 本堂の前には寺号にまつわる伝説の鶴の像が向かい合っていた。 所在地 徳島県勝浦郡勝浦町
|
| 21番札所 舎心山 太龍寺 拡大 |
 |
 |
 |
20番札所から 6.7km、車27km。
標高 520mにある寺で、昔から焼山、お鶴とならぶ三大難所と云われていたが、いま全長
2775mのロープウェーが開通しています。 また、切り返しが必要な細い参道を車で登り、キ ツイ坂道を 1kmほど登ると山門です。 境内では多くの参拝者がいたが、このキツイ坂道若いお遍路さん一人だけでした。 山門
をくぐり、護摩堂、庫裏などを右に見て石段を登り、鐘楼門の先の長い石段を登りきると正面 奥に本堂、右奥が大師堂です。 多くの堂塔が建ち並ぶ姿から 「西の高野山」 とも呼ばれています。
所在地 徳島県阿南市加茂町竜山
|
| 22番札所 白水山 平等寺 拡大 |
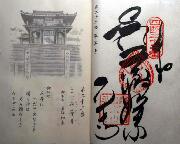 |
 |
 |
21番札所から 10.9km、車14km。
緑・紫・白・赤・黄と色鮮やかな五色の幕を掲げ、小高い山を背に建っていた。
仁王門をくぐると、前方に 42段の石段・男厄坂があり登り切ると本堂です。
そして、本堂側の不動堂前には 33段の石段・女厄坂があり、これを登り下りすることによって
厄を逃れることができるとか。 本堂右から裏山へ続く細い道には、数メートル間隔で観音像が祀られています。
男厄坂の左下に寺号のいわれとなった 「白水の井戸」 があり霊水が湧き出していた。
所在地 徳島県阿南市新野町秋山
|
| 23番札所 医王山 薬王寺 拡大 |
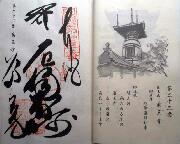 |
 |
 |
22番札所から 19.7km、車 24km。
太平洋を望む山の中腹に建つ寺で、厄除けの寺として有名です。
仁王門をくぐると、左に延びる白壁の参道、33段の女厄坂、鐘楼の先に 42段の男厄坂、そ
の上が本堂、大師堂です。本堂右の 61段の還暦厄坂を登ると朱色の鮮やかな瑜祇塔です。 それぞれの厄坂には 1段ごとに 一円玉などが点々とあり、厄銭を置いて厄をのがれるとい
う風習のようです。 所在地 徳島県海部郡日和佐町
|
| |